
みなさんこんにちは、NIWA colorです。
今回は、高齢者の方が安心して暮らせる庭づくりについてご紹介します。
お庭は心を癒す素敵な空間ですが、年齢を重ねるとちょっとした段差や動線の不便さが大きな負担になることも。
この記事では、転倒リスクを減らすためのポイントや、快適性を高めるための工夫、補助制度の活用方法まで、実用的な情報をわかりやすくまとめています。
将来を見据えたやさしい庭づくりのヒントとして、ぜひご参考ください。
高齢者にとっての庭の危険とは?よくある悩みとリスクを解説

年齢を重ねると、日常の中にあるちょっとした段差や傾斜が、大きな危険につながることがあります。
庭という空間は癒しや趣味の場でもありますが、実は高齢者にとっては注意が必要なポイントが多く潜んでいます。
特に、転倒やつまずきによるケガは、生活の質に大きく影響するため、庭の安全性を見直すことがとても大切です。
まず注意したいのは、敷石や飛び石の段差や傾きです。
長年の経年劣化や地盤のゆるみで、石がガタついたり高さが不揃いになっていたりすることがあります。
こうした部分につまずいて転倒してしまうケースは少なくありません。
また、庭は雨や露で濡れると滑りやすくなる場所でもあります。
タイルやコンクリート、ウッドデッキなどは見た目は良くても、濡れるとツルツル滑ってしまう素材もあるため注意が必要です
。特に足腰が弱くなった高齢者にとっては、歩くこと自体が慎重になるので、素材選びやメンテナンスが重要になってきます。
草が生い茂った庭も、実は危険のひとつ。
雑草の中に隠れている段差や穴に気づかず、足を取られてしまうことがあります。
また、庭仕事が好きな方でも、しゃがんだり立ったりの動作が多いと、ひざや腰に負担がかかり、疲労がたまりやすくなります。
視力や判断力が衰えてくると、昼間でも陰になった場所が見えにくく、物にぶつかったり踏み外したりすることもあります。
夜間に関しては、庭に出ることは少ないとはいえ、センサーライトがなかったりすると、万が一の移動時に危険が伴います。
このように、庭という空間は美しい反面、高齢者にとってはリスクが潜む場所でもあります。
安心して過ごせるようにするためには、危険になりそうな要素を早めに把握して、必要な対策をしておくことが大切です。
安心・快適な庭づくりのポイント3選

高齢者にとって庭は癒しの空間である一方で、体の変化に合わせた設計がされていないと、負担や危険の原因にもなります。
安心して庭時間を楽しむためには、安全性だけでなく、快適に使える工夫を取り入れることが大切です。
ここでは、実際に多くの施工例でも取り入れられている、快適な庭づくりのための3つのポイントを詳しく紹介します。
すべりにくく歩きやすい素材を選ぶ
庭の地面の素材は、安全性と快適さの両方を左右する重要な要素です。
年齢とともに筋力やバランス感覚が低下する中で、つまずきや転倒を防ぐためには「すべらない」「安定している」「段差がない」といった条件が必要になります。
特におすすめなのは、インターロッキングや樹脂舗装といった素材です。
これらは表面がザラついていて、雨の日でも滑りにくいのが特長です。
さらに、雑草が生えにくいため、草抜きなどの手間も減らせます。
素材だけでなく、地面に傾斜がつきすぎないように整えることで、歩くときの脚への負担を軽くし、より安心して庭を歩けるようになります。
たとえば、階段をなくしてなだらかなスロープにする、飛び石の隙間を埋めてフラットにするなどの工夫を加えると、庭全体の安全性が高まります。
シンプルで分かりやすい動線にする
庭のレイアウトは、使いやすさを考えた「動線設計」がとても大切です。
動線とは、家から庭に出て、花壇や物置、ベンチなどへ自然に移動できるルートのことです。
通路が複雑だったり、行き止まりがあったりすると、移動が億劫になり、つまずきや迷いにもつながります。
高齢者にとって安心な動線は、できるだけ直線的で見通しが良いことが理想です。
特に玄関やリビングから直接出入りできる位置に通路を設け、花壇や休憩場所までスムーズに行けるようにすると、庭の活用度がぐっと上がります。
通路の幅は、最低でも70cm以上、将来のことを考えるなら90cm程度あると車いすや手押し車でも安心して通れます。
照明を配置したり、段差があればスロープに切り替えたりすることで、誰にとっても使いやすい庭になります。
休憩スペースと日よけの確保
庭に長くいると、想像以上に体力を消耗します。特に高齢の方は、少しの作業でも疲れやすく、直射日光に当たり続けることで熱中症のリスクも高まります。
そうした負担を減らすためにも、「休憩できる場所」と「日陰になる場所」をあらかじめつくっておくことが大切です。
ベンチやガーデンチェアなどを設置するだけでも、気軽に腰掛けられる場所ができ、庭仕事の合間にひと休みできます。
さらに、パーゴラやオーニングといった日よけ設備を使えば、日差しの強い日でも涼しく過ごせる空間になります。
つる性植物を使ってグリーンカーテンにすると、見た目にも涼しげで癒しの効果が高まります。
休憩スペースの近くに水道や小さなテーブルがあると、ちょっとしたガーデンカフェのような使い方もでき、庭の時間がさらに楽しくなります。
外構に取り入れたい設備

外構に安全性や使いやすさを意識した設備を取り入れることで、庭や玄関まわりでの移動がぐっと楽になり、日々の暮らしに安心が生まれます。
ここでは、特に取り入れておきたい設備を紹介します。
手すりの設置で転倒リスクを減らす
高齢になると、足腰の力が弱くなったり、バランスをとるのが難しくなったりして、玄関ポーチや庭の段差でつまずくことが増えます。
そんなときに役立つのが、移動をしっかり支えてくれる「手すり」です。
設置場所としては、玄関階段・スロープ・アプローチの曲がり角・庭へ降りる段差などが優先されます。
高さは一般的に75〜85cm程度が目安で、握りやすい丸型か楕円型の形状が適しています。
素材は、雨や湿気に強く、滑りにくいアルミや樹脂系がおすすめです。
表面に細かい凹凸や滑り止め加工がされているものを選ぶと、濡れた手でもしっかり握ることができます。
見た目もスタイリッシュなものが多く、機能性とデザインを両立できる手すりも増えています。
センサーライトで足元をしっかり照らす
夕方から夜にかけて、庭やアプローチが暗くなると、段差に気づかずつまずいたり、見えづらい障害物にぶつかるリスクが高まります。
こうした事故を防ぐために効果的なのが「センサー付きの照明」です。
このライトは、人が近づくと自動で点灯する仕組みで、照明のオンオフを自分で操作する必要がありません。
両手がふさがっているときや、暗がりの中でスイッチを探す必要がなく、とても便利です。
設置場所としては、門柱・玄関・階段・通路・物置の周辺など、転倒しやすい場所や行き来の多い場所がおすすめです。
足元を照らす「ローポールライト」や、壁に取り付ける「ブラケットライト」、埋め込みタイプの「グランドライト」など、用途に合わせた選び方ができます。
LEDタイプのものなら省エネで寿命も長く、電気代も抑えられます。
インターホンやポストは使いやすさを重視
玄関先のインターホンやポストは、来客応対や郵便物の受け取りに欠かせない設備ですが、意外と「かがむ・のぞく・歩いて出る」といった動作が高齢者にとっては負担になることがあります。
インターホンは、カメラ付きでモニターに映像が表示されるタイプが安心です。
訪問者の顔がはっきり確認できるため、不要な対応を避けられます。
また、最近はスマートフォンと連動できるタイプもあり、室内にいなくても外出先で応対ができるものも登場しています。
ポストは、できるだけ立ったまま取り出せる高さに設置するのが理想です。
腰を大きくかがめる必要がない高さ(およそ90〜100cm)が使いやすいとされています。
表札・ポスト・インターホンが一体となった「機能門柱」にすると、すっきりまとまり、デザイン性にも優れます。
配置を工夫するだけでも、日々の負担を軽くし、安心感のある外構になります。
ガーデンリフォームで介護保険や自治体補助金を活用する方法
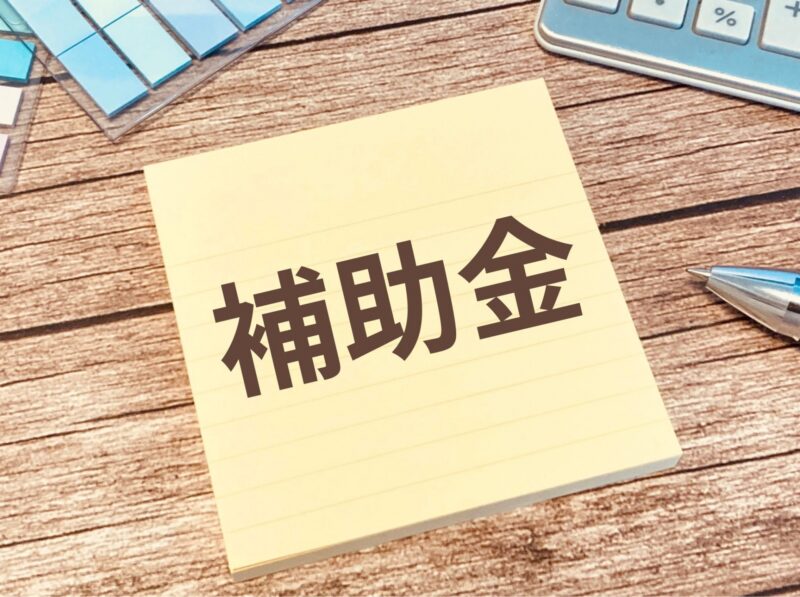
庭のリフォームは、見た目を整えるだけでなく、高齢者が安心して暮らすための重要な生活基盤のひとつですが、介護が必要な方や今後を見据えて住まいを整えたいという方にとって、経済的な負担は大きな問題になります。
そんなときに活用できるのが「介護保険の住宅改修制度」や「自治体の外構・バリアフリー工事に対する補助金」です。
介護保険制度のなかには、要介護・要支援の認定を受けた方を対象に、自宅のバリアフリー改修にかかる費用の一部を補助してくれる制度があります。
1人あたりの上限額は20万円までで、そのうち9割(最大18万円)まで支給されます。
対象となる工事には、手すりの取り付けや段差の解消、滑りにくい床材への変更などが含まれます。
庭まわりに関しては、アプローチのスロープ化や外階段への手すり設置などが該当するケースがあります。
また、自治体によっては独自のバリアフリー改修助成を行っているところもあり、介護保険と併用可能な場合もあります。
例えば、千葉県内の一部市町村では、介護保険対象外となる工事にも補助が出ることがあります。
工事の内容や金額によって支援内容が異なるため、事前に市役所や地域包括支援センターに相談しておくと安心です。
申請の際は、事前にケアマネージャーや住宅改修業者と打ち合わせをして、必要な書類を準備します。
申請前に工事を始めてしまうと補助の対象外になるため、スケジュールには注意が必要です。
実際の工事は、介護保険に対応した業者に依頼することで、手続きもスムーズに進みます。
費用の面で迷っている方にとって、補助制度を上手に使うことは非常に大きなメリットになるので、将来を見据えて、安心して使える庭を整えるために、こうした制度を活用することを検討してみてはいかがでしょうか。
将来も安心して暮らせる庭づくりのために意識したいこと

庭づくりというと、今の暮らしや趣味に合わせた設計を考えることが多いですが、将来の生活まで見据えておくこともとても大切です。年齢を重ねたときに無理なく過ごせるように、あらかじめ意識しておきたいポイントをご紹介します。
ゆとりある通路と移動しやすい配置を意識する
将来、歩行補助器や車いすを使うようになったときに備えて、通路の幅は最初から広めに確保しておくと安心です。目安は90cm以上。
家族や介助者と並んで歩ける広さがあると、移動がぐっと楽になります。
通路は直線的で見通しが良い形にして、曲がり角を少なくするのもポイントです。
余裕のある動線設計は、年齢を問わず快適さにつながります。
お手入れが少なくて済む庭にしておく
高齢になると、しゃがんだり立ち上がったりする動作が負担になることがあります。
雑草の処理や水やりなど、日々の手入れが負担に感じられる前に、手間を減らせる工夫を取り入れておきましょう。
たとえば、防草シートや砂利を使って雑草が生えにくい地面にしたり、自動散水装置を導入するのもおすすめです。
植える植物も、常緑で手入れの少ない種類を選ぶと安心です。
ライフステージの変化に対応できる空間設計
庭は、子育てや趣味、家族構成の変化によって使い方が変わる場所でもあります。
最初は子どもが遊ぶためのスペースとして使っていた場所を、将来的に畑やくつろぎの場所に転用することもあるでしょう。
固定的に作り込まず、自由に使い方を変えられる「余白」を残しておくと、暮らしの変化に柔軟に対応できます。
花壇やフェンスなども、移動や組み替えがしやすいように設計しておくと便利です。
まとめ
高齢者にとって安心して過ごせる庭をつくるためには、安全性と快適さの両立が欠かせません。
転倒のリスクを減らすための段差解消や滑りにくい素材の選定、見通しの良い動線づくりなどの工夫が重要です。
手すりや照明といった外構設備を整えることで、移動や来客対応もスムーズになります。
また、将来を見据えて、通路幅や手入れのしやすさ、空間の可変性を意識することで、長く快適に使える庭になります。
介護保険や自治体の補助制度も上手に活用し、無理なく安心できる住環境を整えましょう。




